主人公はアメリカ国家安全保障局の契約社員のリアリティ・ウィナー、主演はシドニー・スウィニー
アメリカ国家安全保障局(NSA)の契約社員、リアリティ・ウィナー(シドニー・スウィニー)の82分にわたる一幕劇、それが『リアリティ』だ。監督ティナ・サッターの手腕は、ドキュメンタリーとも劇映画ともつかぬこの作品を、まるで我々が覗き見るFBIの尋問記録のように仕立て上げた。シドニー・スウィニーの抑制された演技は、若くして国家の機密に触れる女性の複雑な内面を、静かな迫力で浮かび上がらせる。悪くないが、どこか物足りないのはなぜだろう?
物語は、2017年6月3日、ジョージア州オーガスタの平凡な午後から始まる。リアリティが仕事を終え、車で帰宅すると、突然FBIの捜査官たちが現れる。見知らぬ男たちが家を囲み、まるでカフカの小説のように淡々と、しかし確実に彼女を追い詰める。「家宅捜索の令状がある」と告げる彼らの声は、まるで日常会話のように穏やかだ。だが、その裏には国家の重い影がちらつく。
リアリティはパシュート語、ペルシャ語、ダリー語を操る言語の専門家。彼女の知性は、尋問のさなかでも垣間見えるが、同時にその知性が彼女を窮地に追い込んだ皮肉が、物語の骨子だ。
映画の前半は、FBI捜査官ジャスティンとウォーリーによる、じわじわと核心に迫る尋問のプロセスが描かれる。リアリティが飼い猫にリードをつけたり、犬を裏庭に連れ出したりする日常の仕草が、緊迫感と奇妙な対比をなす。
彼女がPKIパスワード付きのメールを印刷し、スタバに持ち出したエピソードや、NSAのサイトの記事を裏紙として使っていたと語る場面は、まるで現代のデジタル社会における「機密」の脆さを象徴している。機密情報とは、かくも簡単に紙切れ一枚に宿り、そして漏れるものなのか。
見どころは、ラスト21分。リアリティがTorブラウザの使用をほのめかし、ついに印刷した資料をネットに漏洩した事実を打ち明ける瞬間だ。ここで映画は一気に加速し、彼女の動機――国家への疑問か、単なる過失か、はたまた若さゆえの衝動か――が観客の胸に突き刺さる。シドニー・スウィニーの表情は、罪の意識と自己弁護の間で揺れ、観る者の心を掴んで離さない。
だが、この映画、どこか物足りない。――「機密情報の漏洩は、まるでコーヒーをこぼすように簡単だ。しかし、なぜ彼女はそんな危険を冒したのか? そこに踏み込む深さが、この映画にはもう一歩欲しかった」。確かに、リアリティ・ウィナーの内面や動機は、尋問の会話を通じて断片的にしか見えてこない。彼女が国家に抱いた不信感や、現代の情報社会における個人の無力感は、ほのめかされるだけだ。もっと彼女の心の奥底にカメラが潜り込んでいれば、この82分はさらに重みを増しただろう。それでも、この映画が投げかける問いは重い。
機密情報を扱う者に求められるのは、完璧なシステムか、それとも完璧な人間か? 答えは出ないが、少なくとも定期的なチェックと、情報の「重さ」を理解する教育が必要だと、誰もが思うはずだ。『リアリティ』は、派手なアクションも爆発もない。ただ、静かな会話の中で、個人の選択と国家のシステムが衝突する瞬間を、冷徹に、しかしどこか人間的に描き出す。それだけで、十分に価値がある。
このサイトはアフィリエイト広告を掲載しています。
amazonプライムを無料で試してみる ConoHa AI Canvas
楽天市場
マイキッチン
【駐車違反警告ステッカー】の購入|オリジナル印刷・販促のWTP企画
FREE STYLE
医療美容特化ロロント


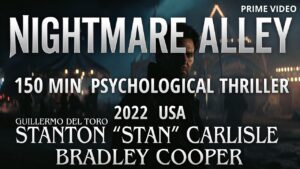






コメント